病気やケガで入院や自宅療養をしている時に友人や知人からお見舞いをいただいた場合は快気祝いや退院内祝いをお返しするのがマナーですよね。
ただ、病気治療中に残念ながら亡くなってしまうこともあります・・・。
そんな場合は何かお返しするべきなのか、また、返す場合の時期(タイミング)やお返しの品物の相場はどのくらいが適切なのか?
ケース別にご案内します。
亡くなった場合のお見舞いのお返しは?
残念ながら亡くなってしまった場合でもお見舞いのお返しは時期を見て返すのが一般的なマナーです。
では、どのようなパターンがあるのか順番にみていきましょう。
お見舞いのお返し(御礼)として返す場合
お見舞いをいただいたけどお香典はいただいていない場合は「御見舞御礼」としてお返しします。
最近ではお通夜、お葬式の際に「香典辞退」で香典をとらない場合が増えていますのでお見舞いのお礼としてお返しします。
この場合の品物に付ける「水引き」は「御見舞御礼」と書き「不祝儀用」の水引を選びます。
水引の色は地域によって違いがあるので確認してください。
また、金額はもらったお見舞いの2分の1~3分の1を目安にお返しします。
香典返しにお見舞いのお返しを含めて返す場合

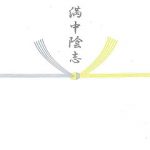
 お見舞いも香典もいただいた場合は香典返しに御見舞御礼を含めてお返しをすることもあります。
お見舞いも香典もいただいた場合は香典返しに御見舞御礼を含めてお返しをすることもあります。
一般的に香典返しの相場は「半返し」と言われていますので香典の2分の1の金額の相当品をお返しします。
また、お見舞い返しは2分の1~3分の1が相場ですので、「香典返し」と「お見舞いのお礼」を足した金額相当品をお返しします。
例えば「お見舞いで1万円」「香典で1万円」合計2万円いただいた場合は1万円までの品物をお返しします。
水引の上書きは「志」「粗供養」「満中陰志」「忌明志」など四十九日の法要の後に香典返しとしてお返しします。
香典返しの水引の書き方は「地域」や「宗派」によってしきたりがありますので確認した方が無難です。
また、水引の種類も「藍銀の水引(主に東日本)」「黄白の水引(主に西日本)」「蓮絵入りの水引(一部の地域)」と複数あります。
香典返しとお見舞いのお返し(御礼)を別々に返す場合
それぞれ別の品を返す場合もあります。
この場合は、
- お見舞いのお返しは「2分の1~3分の1」
- 香典返しは「半返し(2分の1)」
でお返しします。
水引の表書きはそれぞれ
- お見舞いのお返しの場合・・・御見舞御礼
- 香典返しの場合・・・志、粗供養、満中陰志、忌明志など
このように書きます。
また、注意点として
それぞれの品は同じ日に届けずに日をずらして届くようにしましょう。
これは「品物が重なって届く=不幸が重なる」ということから縁起が悪いとされているからです。
御見舞御礼や香典返しに適切な品物は?返す時期は?
食べて無くなる食品や使ってなくなる消耗品がおススメです。
具体的には
- 海苔
- お茶、コーヒー、紅茶
- 石鹸
あと、以下のように複数のものを合わせたお返しもおススメです。
- 食品+カタログギフト
- 消耗品+カタログギフト
また、地域によって贈らない方が無難な品物もあります。
- かつお節
- 昆布
これらはお祝い事の品物のイメージがあるのでもらった方の心象を考えた場合、避けた方が無難です。
また、お返しする時期は四十九日の法要を済ませた後に適切な包装でお贈りします。
まとめ
今回は治療の甲斐もなく亡くなってしまった場合のお返しについてでしたが全快のお返しについてはこちらもご参考にしてくださいね。
亡くなったことは残念ですが、生前の故人に対する心遣いに対して最善の礼を尽くしたいものです。
お見舞いだけをいただいた場合やお見舞いと香典をいただいた場合などケースによって適切にお返しをしましょう。

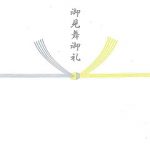



コメント